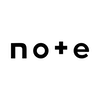A
Al Schmitt:グラミー賞23回受賞歴のあるレコーディングエンジニア兼プロデューサー。
Alfred Lion:ブルーノートの創設者でプロデューサー。
ARUN:Arun Chakravertyの略。レコーディング&マスタリングエンジニアの刻印を表す。
AT:デッドワックスにある刻印のことで、Atlanticスタジオの意味。
赤盤:赤い色のレコード盤のこと。基本的に黒い色のレコードが主流。
アセテート盤:レコードの量産化に入る前に、音圧チェックやミキシングなど最終確認のために作られるアセテート素材のテストプレス盤のこと。
アダプター:レコードのアダプターといえば7インチ(EP)アダプターを指す。※7インチアダプター参照。
アビーロードスタジオ:ビートルズがレコーディングを行ったことで有名なロンドンのレコーディングスタジオ。
B
Bell Sound:デッドワックスにある刻印のこと。Bell Sound Studiosでマスタリングやカッティングしたことを意味する刻印。またはエンジニアのSam Feldmanを指す場合もある。
BG:Bernie Grundman(バーニーグランドマン)の略。デッドワックスにあるBG刻印のこと。日本でも人気の高いマスタリングエンジニアで、ハリウッドのみならず東京にも自身のマスタリングスタジオを開業。
BPM:Beat Per Miniteの略称。楽曲のテンポ(速さ)を表す言葉。1分間の拍数を表す。
盤起こし:オリジナル音源のマスターテープがない(紛失した)場合に、レコードを再生してマスターテープを作ること。なので、スクラッチノイズが入ってるCD(レコード)等もしばしばある。
盤反り:ヒートダメージや保存状態により、ゆがんで反ってしまったレコード盤のこと。
ビートメイカー:元々はヒップホップ界隈で、楽曲の伴奏トラックを制作する人、またはインストゥルメンタルを制作する人を指すスラングだが、海外では「プロデューサー」に近いニュアンスで使われる。日本ではトラックメーカーとも呼ぶ。(例:J Dilla、Pete Rock、Nujabesなど)
ブート(Boot/Bootleg):ブート盤、ブートレグ、ブートレッグ、海賊盤。アーティストやレコード会社の許可を得ていない非正規のレコード。
ブレイク:主に楽曲内で一時的に音が停止して空白になる「つなぎ」部分のこと。他の楽器演奏が止まってドラム音だけになる部分をドラムブレイクと呼ぶ。
C
CB:マスタリングエンジニアでバーニーグランドマンの弟子、Chris Bellmanの略。デッドワックスにあるCB刻印のこと。
Chris Blair:アビイロードのハウスエンジニア。レディオヘッドのアルバムでグラミーを受賞した。
Colour Vinyl:カラーヴァイナル。色の付いたレコード盤のこと。基本的に黒い色のレコードが主流。
Cover(カバー):ジャケットのこと。海外でレコードジャケットのことを、主にCoverやSleeveと言う。※ここでは「他人の楽曲をカバーする」のカバーとは別の意味。
CS:Company Sleeve(カンパニースリーブ)の略。レコード会社が配布する宣伝用の内袋のこと。
Cut:カット、ジャケットの角やフチにある切り込み跡や貫通穴のこと。
カッティング:レコードに音声と同じ物理的な溝を掘る作業。その作業を行う技術者をカッティング・エンジニアと呼ぶ。
カートリッジ:レコード針のこと。厳密には、レコード針は「カートリッジ」と呼ばれるパーツの一部。針先だけ交換も可能。
クラシック:定番や名盤のこと。ここでは、いわゆる西洋クラシック音楽のことではなく、DJやヒップホップ界隈で、定番や名盤のことを指すスラング。今やレコード用語の一つになっている。
コーティングジャケット(コート&ラミネート):表面に艶のある光沢加工を施されたジャケット仕様のこと。
コラボ:コラボレーションの略。共演、合作、共同作業などの意味。
コンピ:コンピレーションの略。コンピレーション・アルバムのこと。編集盤、ベスト盤、オムニバスなどと類似。
センターホール:レコード盤の中央の回転軸の穴のこと。
センターラベル:レコード中心部に貼付された(主に曲目など記載されている)円形ラベルのこと。センターレーベルとも言う。
蓄音機:主にSPレコードを再生するための装置。
D
David Foster:グラミー賞を15回獲得したプロデューサー兼作編曲家。
DBH:David B.Hancockの略。レコーディング、マスタリング&カッティング・エンジニアの刻印を表す。初期はDH刻印。
DG:Deep Groove(ディープグルーヴ)の略。レコードのラベルにある深い溝のこと。主に1950年代~1960年代のレコードに多い。
DHカット:ドリルホールカットの略。ジャケットにドリルで開けた貫通カット穴のこと。
Direct Cutting(ダイレクトカッティング):ダイレクトカットとも呼ぶ。レコード制作方式の一つで、オリジナルテープへの録音・編集・マスターテープの作成というプロセスを通さず、演奏をそのままリアルタイムでディスクに刻むこと。
Direct Disc(ダイレクトディスク):オリジナルテープへの録音・編集・マスターテープの作成というプロセスを通さず、演奏をそのままリアルタイムで刻んだレコード盤のこと。メンバー全員での一発録音でアルバム片面を一気に行うため、高度な演奏技術が要求されるので、ジャズやクラシックのレコードに多いのも特徴の一つ。
DJ:Disc Jockeyの略。クラブなどで、そのフロアの雰囲気に合うレコードを選曲し音楽をかけて盛り上げる人。または、ラジオ番組などで音楽を選曲して流す人のこと。
DMM:ダイレクトメタルマスタリング(Direct Metal Mastering)の略。銅製のメタルディスクに直接溝を刻むレコードのカッティング技術の方法。
DTM:デスクトップミュージック(Desktop Music)の略。パソコンを使用して楽曲を作る音楽制作手法の総称。
ダイカット:ダイカットスリーブの略。レコード保存用の厚紙ジャケットのこと。EP用、10inch用、LP用、センターホール付き等ある。
駄盤(だばん):価値の低い期待外れのレコード。
ダブ:元々はレゲエから派生した音楽制作手法のことで、今や音楽ジャンルの一つとして確立。元の楽曲にエコーやディレイなどのエフェクターを過剰に施した音が特徴的で、新たに楽曲をミックスし直すこと。リミックスの原点とも言われている。
ディグる:「掘る」という意味の英語「dig」から派生した言葉で、DJなどがレコードショップでレコードを探す(掘る)という意味からきたスラング。情報を探す、探求、発堀するという意味もある。
デッドストック:当時の未開封品が長期間放置され手つかずの状態で眠っていた貴重プレミア在庫品。
デッドワックス:レコード盤の溝の一番内側とセンターラベルの間の無音スペースの溝がないツルツルした部分を指す。ランアウトやランオフ、テイルオフとも呼ばれる。
デフジャケ/デフジャケット:Different Jacketの略。(同内容なのに)オリジナルと異なるジャケットデザイン。別ジャケット、独自ジャケットとも言う。
ドーナツ盤:7inchのEP、シングルレコード。主に45回転。
E
Eddie Kramer:ジミヘンの主要アルバムほぼ全作に関わったことでも有名なプロデューサー兼レコーディングエンジニア。
EP:Extended Playの略。45回転の7インチシングル・レコードのことをEP盤と呼ぶ。
EU盤:ヨーロッパ(European Union)盤の略。ヨーロッパでプレスされたレコード盤のこと。
Excellent(EX):綺麗な状態のこと。主に海外でのレコードコンディション表記の一つ。日本ではABC表記が一般的。
エロジャケ:エロいジャケット(写真やデザイン)のこと。
エンボス:ジャケット表面の一部が凹凸した浮き出し加工されているジャケット仕様のこと。
塩ビ:塩化ビニールの略。LP以降のレコード盤の主となる原材料。
塩ビ焼け:質の悪い塩化ビニール製の内袋やジャケットスリーブに入れていたことにより、レコード盤の表面が白っぽく焼けた状態のこと。
F
F(Fair):不良品。ジャンク品。POORとも呼ぶ。状態が非常に悪い。主に海外のレコードコンディション表記の最低ランク。
FBジャケット:フリップバック・ジャケットの略。ジャケット裏の上下に折り返しがある薄手ジャケット仕様のこと。E式ジャケット、またはペラジャケとも呼ばれている。
FLAT:平らな状態のこと。レコード盤の端にGroove Guardがない平らな状態をFLAT盤。ラベルが平らな状態をFLATラベルと言う。
フィーチャリング:メインのミュージシャンの楽曲にゲスト参加すること。
フルコーティングジャケット:フルコート、フルコーティングスリーブとも言う。ジャケットの表と裏の全面がコーティングされているジャケットのこと。フルコーティングに対して、表のみコーティングがあり裏面はコーティングがないものをフロントコーティングジャケットと呼ぶ。
G
G:Goodの略。主に海外でのレコードコンディション表記の一つ。日本語に訳すと「良い」だが、実際には致命的なキズや擦れが多く一般的には非常に悪いジャンク品を指す。あくまで海外のコンディション表記の基準なので、日本人の感覚からすれば、全く「良い」とは言えない。
Gary Katz:レコードプロデューサー。スティーリーダンのほとんどの作品を手掛けたことで有名。
Generic:代替品、またはジャケット無し。主に海外でのレコードコンディション表記の一つで、オリジナルジャケットではないプレーンのジャケットを指す場合など。
George Marino:マスタリングエンジニア。刻印は、M.B.G.(Mastered By Georgeの略)。
George Martin:ビートルズの主要アルバムほぼ全作品を手掛けたことで有名なプロデューサー。「5人目のビートルズ」と称された。
GFジャケット:ゲートフォールドジャケットの略。見開きジャケットのことで、ダブルジャケットとも言う。
GG:Groove Guard(グルーヴガード)の略。レコード盤の端にある僅かな膨らみのこと。
Gilles Peterson:レコードDJカルチャーに多大な影響を与えた、90sクラブシーンとアシッドジャズムーブメントの立役者、DJ兼プロデューサー。
GP:デッドワックスにある刻印のことで、マスタリング&カッティングエンジニア、George Pirosの略。
Greg Calbi:主にSterling Soundスタジオ専属のカッティング&マスタリングエンジニア。刻印は「gc」など
額縁ジャケット:ジャケットスリーヴの三辺(または二辺)が内側で重なって盛り上がっている構造のもの。壁かけ額縁のフレーム部分に似ているため。
ゴールドスタンプ(Gold Stamp):ジャケットにある、プロモ用を示すGoldのスタンプ押印。
誤表記(誤植/Misprint):最初は(ジャケットやラベルに)表記ミスのまま発売されたが、再度プレスする際に修正し直して再発したりする。その場合は(誤植ジャケか修正ジャケか等)1stプレスと2ndプレスを見分ける判断材料になる。
H
Howie Weinberg:ニルバーナの「Nevermind」などを手掛けたことでも有名なマスタリングエンジニア。
ハーフスピードカッティングorマスタリング:マスター音源をハーフスピードで再生しながらマスタリング/カッティングを行うこと。それにより音質向上効果があるとされる。
ハイプステッカー(Hype Sticker):ジャケットに直接(またはシュリンク上)貼り付けられた広告宣伝用のステッカーのこと。
発禁ジャケ:発売禁止ジャケットの略。一度は発売されたものの、ヌードや不謹慎などの理由で途中で発売禁止になり、お蔵入りとなったレコードジャケットのこと(ジャケットデザインを差し替えて再発売された例も少なくない)。
針飛び:傷や振動などでレコードの溝を針がずれて違う溝に飛ぶこと。
ヒートダメージ:熱のダメージを受けたレコードのこと。針飛びを生じることもある。
ヒゲ:レコードラベル面のセンターホール周りに付いた、擦った跡のこと。
ヒプノシス(Hipgnosis):ジャケットデザインを手がけるイギリスのグラフィックデザイン集団。
ヘアライン:レコード盤に、まるで髪の毛(ヘア)のような薄いキズがあること。
掘る:レコードショップでレコードを探す(掘る)行為のこと。=Dig(る)。
I
INNER:インナー/インナースリーヴの略。レコードを入れる内袋のこと。
INSERT:インサート。歌詞や解説などが印刷された付属の紙のこと。
INSV:インナースリーヴの略。レコードを入れる内袋のこと。
J
ジャケ買い:レコードの内容を知らずにジャケットのデザインだけに惹かれて購入すること。
ジャケ違い:ジャケットのデザインが違うが、内容が同じレコードのこと。あえて違うジャケでコレクションする人もいるが、大抵は間違って買ってショックを受けることが多い。
ジャケット:またはレコード盤を入れる外装のこと。ジャケットスリーヴまたはディスクジャケットとも呼ぶ。海外ではスリーヴ(Sleeve)やカバー(Cover)とも呼ぶのが一般的。
重量盤:通常よりも重い180gや200gのレコード盤。通常のLPレコードは140g程度。重量があることで回転が安定して、音の揺らぎや歪みが抑えられる。
12inch:サイズはLPと同じ。レコード業界で12inchといえば、12インチシングル(片面1~2曲程度の45回転)を指すことが一般的。HipHopやテクノなどクラブミュージック系レコードが多く、DJなどに人気。
K
KENDUN:Kent Duncanの略。KENDUN刻印のこと。Kent Duncanが設立したKendun Recordersスタジオでマスタリング&カッティングされたことを表す、デッドワックスに押された刻印のこと。
Kevin Gray:主にAnalogue Productionsなどを担当する現代最高峰のマスタリング&カッティングエンジニアの一人。刻印は「KPG」など。
カゼヒキ:質の悪いレコード盤の素材が原因で起こる、再生時の「サーーー」という終始ノイズがしている状態のこと。
角打ち:ジャケットの角に打つけたような跡やシワがあること。
神成芳彦:日本を代表するレコーディングエンジニア。日本のルディヴァンゲルダーと呼ばれた。
キズ(傷):レコード盤の状態において、「ブツ...ブツ...ブツ...」のような周回ノイズの出るような深いキズ(傷)のことを意味する。「スリキズ(擦り傷)」とは似て非なるもの。
検盤:レコードショップで購入する際に、レコードの盤面の状態を確認すること。
高音質盤:音質の良いレコードのこと。優秀録音や重量盤など定義は幅広い。傷やノイズがあるなどの盤質状態の良し悪しとは別の意味。
国内企画盤:日本国内で企画されたレコード。海外アーティストによる日本録音、来日公演のライブ盤など、日本盤がオリジナルということで海外コレクターからも人気が高い。
小鉄徹:日本を代表するマスタリング&カッティングエンジニア。
L
LATE:再発盤のこと。基本的には、数年〜数十年経過した後年プレス盤のことを指す。
LCマーク:LC=Labelcode(レーベルコード)の略で、主にジャケットとラベルに表記されたマーク。1977年ドイツの音楽レーベル保護公社によって付与されたもので、それ以前のレコードに表記はない。
LH:Lee Hulkoの略。Lee Hulkoがカッティングしたことを意味する刻印。
LP:long playの略語。一般的なレコード。主にアルバム収録で、片面の時間が約30分。直径12インチ (30cm) 、33回転(33 1/3rpm)。
LW:デッドワックスにある刻印のことで、ロングウェア社を意味する。
ライナー:ライナーノーツ。日本盤は解説など付属の冊子を指すことが多いが、輸入盤はジャケット裏に印刷されてることが多い。
ラウドカット:レコードをカッティングする際に可能な限り音圧を高くして溝に刻んだレコードのこと。
ラッカー盤:レコードの型をつくるために円盤型に音を刻んで記録する盤のこと。ラッカー盤に音を刻んでマスター盤をつくる。ちなみにラッカー盤の製造工場は世界で唯一日本だけ。
M
Manfred Eicher:ECMレコードの創設者でプロデューサー。
MASTERDISK:Masterdisk Studios社でマスタリング&カッティングされたことを表す、デッドワックスに押された刻印のこと。
MAT:Matrix/マトリックスの略。レコード盤のデッドワックス部分(ラベル付近の音溝のない部分)に刻印されている記号や番号のこと。
MFSL:Mobile Fidelity Sound Lab(モービルフィディリティサウンドラボ)の略。世界のオーディオマニアから絶大な支持を得るリマスター専門のレーベル。
MINT (M):新品同様。主に海外でのレコードコンディション表記の一つ。日本ではABC表記が一般的。
MR/MO:デッドワックスにある刻印のことで、西海岸のモナーク工場を意味する。
MTR:マルチトラックレコーダーの略。ギブソンレスポール生みの親でギタリストのレスポールが、マルチトラックレコーダー技術の開発と進化、実用化に至る最大の功労者とされる。
マーチャントシート(Merchant Sheet):通販案内や広告が掲載されたインサートのこと。
マザー盤:メタルマスターからメッキをとったもの。メタルマザー、ポジティブ(凹)とも呼ぶ。
マスターディスク(マスター盤):流通盤を製造するための複製元ディスクのこと。
マスタリング:レコード制作における最終仕上げ作業のこと。音質や音圧、ミックス調整、曲間バランスなど、最終チェックしてマスター音源(原盤)を作成する作業。
マットコート:マットコーティングジャケットの略。ジャケット表面をツヤ消し加工してあるコーティングジャケットのこと。
耳(Ear)マーク:デッドワックスにある刻印のことで、プレス工場Plastylite社の頭文字である「P」を意味するもので、その「P」が耳の形に見えることから、耳(Ear)マークと呼ばれている。
ムロ (MURO):日本のレコードDJカルチャーに多大な影響を与えた、日本を代表するDJ。
メタルマスター:マスター盤にメッキをかけて型をとった保存用マスターディスクのこと。ファーザー盤、ネガティブマスター(凸)とも呼ぶ。
モノラル(MONO):1つのチャンネルで音声を再生または録音する方式。左右のスピーカーから同じ音が聴こえるのがモノラル。1958年にステレオ盤が普及されるまではモノラルが主流。
N
Near Mint (NM):新品に近い状態。主に海外でのレコードコンディション表記の一つ。日本ではABC表記が一般的。
長岡鉄男:オーディオ評論家。ベストセラー書籍「外盤A級セレクション」などで紹介された優秀録音のレコードが人気を博した。
7インチ:EP、シングルレコードのこと。主に45回転。ドーナツ盤とも呼ぶ。
7インチアダプター:7インチ盤を再生するために必要なアダプター。7インチ盤は中心穴が大きいので、そのままプレイヤーで再生できないため、穴にアダプターをはめてプレイヤーの回転軸に固定させることで再生できる。EPアダプターとも言う。
ニュースクール:元々は90年代以降の新しい音楽スタイルを指す言葉だが、最近はもっと広い意味で使用されることが多い。オールドスクールの対義語の意味合いがある。
猫ジャケ/ネコード:レコードのジャケットに猫が描かれている(または写真)もの。レコードショップや雑誌などで特集が組まれたり、コレクターも存在するほど人気が高い。ネコードとも呼ぶ。
ネタ盤:DJやヒップホップ界隈で、サンプリングネタとして曲の一部をチョイスして使用された元ネタ収録レコードのこと。
O
帯:レコードジャケットに付けられた紙製の帯状広告のこと。レコードだけでなくCDや本にも付いている。今や海外でも「OBI」と呼ばれている。
オールドスクール:古い音楽スタイルを指すスラング。元々は1970~1980年代頃にニューヨークで行われたブロックパーティから登場したヒップホップの初期を意味する言葉だが、今はもっと広い意味合いで使われことが多い。
オブスキュア:直訳すると「不明瞭な」だが、ここでは「あまり知られていない」「日の目を見ない」「レア」という意味で使われるDJやレコード界隈のスラング。ブライアンイーノのレーベル名とは関係ない。
オリジナル:1stプレスの初版のレコード。基本的に、1番最初にプレスされたレコードを指すが、各国それぞれ、アメリカの初版は「US-Original」、イギリスの初版は「UK-Original」、ヨーロッパの初版は「EU-Original」など表記される場合もある。
P
P(Poor):不良品。ジャンク品。Fairとも呼ぶ。状態が非常に悪い。主に海外のレコードコンディション表記の最低ランク。
Pecko/Pecko Duck:イギリスのジョージペッカム(George "Porky" Peckham)がカッティングしたことを意味する刻印。
PHカット:パンチホール・カットの略。ジャケットにパンチで開けた丸い貫通カット穴のこと。
Picture Vinyl:ピクチャー盤。盤面に写真や画像が印刷されたレコード盤のこと。
Porky:「Porky Prime Cut」の意味で、イギリスのジョージペッカム(George "Porky" Peckham)がカッティングしたことを意味する刻印。ビートルズやレッドツェッペリンのカタログ制作など輝かしい経歴を持つ。
PR:デッドワックスにある刻印のことで、プレスウェル工場を意味する。
PROMO/プロモ/見本盤:プロモーション用のレコードのこと。見本盤、サンプル盤、Promotional Copy、Sample Copy、DJ Copy等のこと。
PS:Picture Sleeve(ピクチャースリーヴ)の略。写真や絵がデザインされた内袋のこと。
Phil Spector(フィルスペクター):「ウォールオブサウンド」という独自の音楽制作手法を確立した伝説の音楽プロデューサー。
フォノ(PHONO):レコードを再生・接続するための端子。またはレコード再生機器に関する用語(例:フォノイコライザー、フォノケーブル、フォノカートリッジなど)。
プチノイズ:傷や汚れ、プレスミス等によって発生する「プチ」というノイズ音のこと。
プレスミス:レコード製造時に異物が混入したり不具合が生じてしまった不良盤のこと。
Q
Quadraphonic:4チャンネル方式で録音・再生するレコード。前方ステレオ再生(2チャンネル)と後方2チャンネルで録音・再生することで臨場感のあるサウンド効果が得られる。中には、通常のステレオ盤とは違うテイクやミックスを使用してることもある。
R
RE:デッドワックスにあるRE刻印のことで、カッティング用のマスターテープを更新されたことを示す場合が多い。
Reissue(リイシュー):再発盤のこと。すでに発売されたレコードを、新たに製造し再発売すること。
RL:RL刻印やRLカッティングのこと。マスタリング・エンジニアのBob Ludwig=RL(Robertの愛称がBobのため)の刻印を表す。デッドワックスに掘られた刻印のこと。この刻印があるか無いかでオリジナルか否か判断することもある。
Roy DuNann:レコーディングエンジニア。イーストコーストのルディヴァンゲルダー、ウェストコーストのロイデュナンと呼ばれるほど東西を二分する名エンジニア。
RPM:レコードが1分間に回転する数値のこと。LPは33rpm=33回転、EPは45rpm=45回転、SP盤は78rpm=78回転など。
RVG:Rudy Van Gelder(ルディヴァンゲルダー)の略。レコーディング・エンジニアの刻印を表す。デッドワックスに掘られた刻印のことで、「RVG」「VAN GELDER」、機械打ちや手書き刻印など数種類ある。この刻印があるか無いかでオリジナルか否か判断することもある。
リプレス:再プレス盤のこと。基本的には、初版プレスと仕様変更の無いレコードのことを指す。再発盤とは若干ニュアンスが異なる。
リプロ:reproductionの略。複製品または正規品と確証のないもの。著作権の切れた作品をオリジナルに忠実に再現することもある。オリジナルとの違いはマトリックスの刻印などで判別できる。ブートや海賊盤と類似。
リム:ラベル面の円周に沿って記載されている住所表記や製造表記などのこと。リムの違いによって1stプレスか2ndプレスかなど判断することもある。
リングウェア:ジャケットスリーヴに、盤に沿って丸いスジ状の擦れ跡があること。
レアグルーヴ:直訳すると「珍しいグルーヴ(溝=レコード)」。ファンキーでグルーヴィーな"踊れるジャズやソウル"的な、今や一つの音楽ジャンルとして確立しつつある。元々はDJがブラックミュージックを中心に誰も見向きもしない埋もれた音源にスポットを当てて発掘(再評価)するという行為がレアグルーヴの始まり。DJやヒップホップ界隈では、サンプリングネタとして曲の一部をチョイスして使用された楽曲なども、レアグルーヴクラシック(いわゆるネタ盤)として語られることもある。
レア盤:希少価値の高いレコードのこと。(例:激レア盤、メガレア盤)
廉価盤(廉価版):低価格品。内容を変えずに低価格化した商品のこと。
S
SR:マスタリング&カッティングエンジニアStan Rickerの略で、デッドワックスに掘られた刻印のこと。
SLM:Sheffield Lab Matrix社でマスタリング&カッティングしたことを表す、デッドワックスにある刻印のこと。
SOC:Stecker On Coverの略。ジャケットにステッカーが貼ってあること。
SOL:Sticker On Labelの略。ラベルにステッカーが貼ってあること。
SOBC:Sticker On Back Coverの略。ジャケット裏にステッカーが貼ってあること。
SP:Standard Playの略。古いレコードのタイプで78回転盤のレコードのこと。SPレコード、SP盤=シェラック盤とも呼ぶ。材質はシェラック(樹脂)製で、主に片面に1曲程度の収録。
Stanley Goodall:初期ステレオ盤を手掛けたことで有名なDeccaスタジオ専属のカッティング&レコーディングエンジニア。刻印は「E」。
STERLING:STERLING刻印のこと。ニューヨークにあるSTERLING SOUNDスタジオでマスタリング技師にマスタリングされたレコードのデッドワックスにある刻印。この刻印があるか無いかでオリジナルか否か判断することもある。
Steve Hoffman:AcousTech Mastering社のマスタリングエンジニア。
サバービア:Suburbia Suiteの略。日本のレコードカルチャーに多大な影響を与えた、橋本徹氏が編集のレコードガイド。
サントラ:サウンドトラックの略。映画音楽のこと。
サンプリング:過去の曲の一部をチョイスして流用し、再構築して新たな楽曲を製作する音楽表現方法。あるいは楽器音や環境音をサンプラーで録音し、新たな楽曲に取り入れることもある。
シールド(sealed):S 未開封のこと。
シェイプ盤:円形ではなく、様々な形をしたレコード。シェイプレコード(Shape Record)とも言う。
シュリンク:新品レコードのジャケットに施された外装フィルムのこと。
針圧:レコード針がレコードを下方向に押さえる時の重さ(圧力)のこと。
菅野沖彦:日本を代表するエンジニア、オーディオ評論家。オーディオラボを創立。キースジャレットの「サンベアコンサート」など手掛ける。
スクラッチ:=コスリ。レコードを前後に動かし擦って効果音を作り出すDJの演奏テクニック。
スタイラス:交換針。カートリッジの針先のこと。
スタビライザー:レコード再生時にターンテーブルの回転軸に置く重しのアクセサリーのこと。それによりレコードの振動を抑え安定させ音質を向上させる効果がある。
スタンパー:レコードのプレス機に取り付ける金属製の凸版のこと(マザー盤を型どったもの)。このスタンパーからプレスされてアナログレコードが生産される。プレスする度にスタンパーは消耗するので、またマザー盤から新しいスタンパーをつくり直す。
ステレオ:2つのチャンネルで音声を再生または録音する方式。左右のスピーカーから異なる音響信号を再生する。1958年にステレオ盤が普及されるまではモノラルが主流。
スピンドルマーク:レコードラベル面のセンターホール周りに付いた、擦った跡のこと。
スリキズ(擦り傷):盤質コンディション表記以外の、特記事項に「スリキズ(擦り傷)」と表記がある場合には、音に大きく影響しない程度の薄い傷のことを意味する。※ただし高級オーディオなどを利用する場合は除く。
スリップマット:レコードとターンテーブルの間に敷くマットのこと。
スレ(擦れ):盤質コンディション表記以外の、特記事項に「スレ(擦れ)」と表記がある場合には、音に大きく影響しない程度の薄い擦れのことを意味する。※ただし高級オーディオなどを利用する場合は除く。
背:ジャケットの背表紙部分のこと。(例:背文字、背焼け、背絞り、背ヒビ割れ)
背絞り(Pinched Spine):ジャケット背表紙の上と下だけが絞ってある仕様のこと。ヨーロッパ盤にしばしば見られる
背文字なし:ジャケットの背表紙が全て絞ってあり背文字が無いタイプのジャケット仕様のこと。ペラジャケとは別物。ドイツ盤にしばしば見られる。
2ndプレス:文字通り2回目のプレスのこと。タイトルによっては、オリジナル発売後に数ヶ月も経たないうちに2ndプレスが発売されたり、10年後に2ndプレスが発売されることもある。マトリックス等の違いによって判別されることもあり、コレクターの間ではオリジナル盤の次に価値があるとされることも多い。ちなみに3回目のプレスを3rdプレスと呼ぶ。
センターホール:レコード盤の中央の回転軸の穴のこと。
センターラベル:レコード中心部に貼付された(主に曲目など記載されている)円形ラベルのこと。センターレーベルとも言う。
底:ジャケットスリーヴの下部のこと。(例:底抜け、底ヒビ割れ、底傷み)
ソノシート:ペラペラに薄く軽い廉価版レコードのこと。昭和時代は、主に雑誌や教則本の付録などに使用された。
T
Ted Jensen:数百ものグラミー賞受賞レコードに貢献したマスタリングエンジニア。
TEXジャケ:テクスチャー(Texture)ジャケットの略。織物のような加工がされたザラザラした質感のジャケット素材のこと。
TML:The Mastering Labの略。TML刻印。マスタリングエンジニアのDoug Saxを表すデッドワックスに掘られた刻印のこと。
TOL:Tear On Labelの略。ラベルに剥がし跡があること。
TOC:Tear On Coverの略。ジャケットに剥がし跡があること。
TOBC:Tear On Back Coverの略。ジャケット裏に剥がし跡があること。
Tommy LiPuma:音楽プロデューサー、Verveミュージックグループ会長。
Tri-fold:(=triple) 三つ折ジャケットのこと。観音開きジャケットとも言う。
10inch:直径約25cmのレコード。古いジャズやクラシックのレコードに多いサイズ。一般的なレコードのサイズは、12inchと7inchが主流。
ターンテーブル:レコードプレーヤーのこと。アナログレコードを再生するための装置。
チリノイズ:ゴミや汚れ、傷等の影響により「チリチリ」というノイズ音のこと。
珍盤(ちんばん):昭和時代を中心としたユニークで珍しいレコードのこと。
テストプレス:レコード生産前に、プレスするレコードの音質や溝や曲順などの最終確認用ディスクのこと。基本的に、プロモ盤は販売店に配布された後は破棄されるが、テストプレス盤はレコード会社に返却しなければならない。
天:ジャケットスリーヴの上部のこと。(例:天抜け、天ヒビ割れ、天傷み)
U
UK盤:United Kingdom盤の略。イギリスでプレスされたレコード盤のこと。
Unipakカバー:見開きジャケットを開いて内側からレコードを出し入れする形態になっているジャケットのこと。通常は見開きジャケットを開いて外側から出し入れする。
US盤:United States盤の略。アメリカでプレスされたレコード盤のこと。
V
VG:Very Goodの略。主に海外のレコードコンディション表記の一つ。日本語に訳すと「とても良い」だが、実際には使用感がありキズや擦れが多く一般的には悪い状態を指す。あくまで海外のコンディション表記の基準なので、日本人の感覚からすれば、全く「とても良い」とは言えない。
ヴァイナル:ヴァイナル盤=ビニール盤=塩化ビニール素材を使った一般的なレコードのこと。
W
Wax:海外ではレコード盤のことをしばしばWaxとも呼ぶ。Waxは英語で樹脂という意味もあるので、古いSPレコードが樹脂製で作られていたことに由来する。(例:White Wax、Red Waxなど)
WOL:Writing On Labelの略。ラベルに書き込みがあること。
WOC:Writing On Coverの略。ジャケットに書き込みがあること。
WOBC:Writing On Back Coverの略。ジャケット裏に書き込みがあること。
ウォーターダメージ:ジャケット水濡れによるシミ汚れや変形ヨレのこと。
和モノ:邦楽のこと。元々はDJカルチャーの中で生まれたスラングで、それまで埋もれていた(ダサいと思われてた)昭和の音楽を、DJで使えるネタとして発掘(再評価)するという"レアグルーヴの日本版"みたいなニュアンスに近い。なので和モノの「和」は、日本の「和」という意味もあるが、昭和の「和」という意味合いが強い。ちなみに日本人ジャズを=和ジャズと呼ぶ。